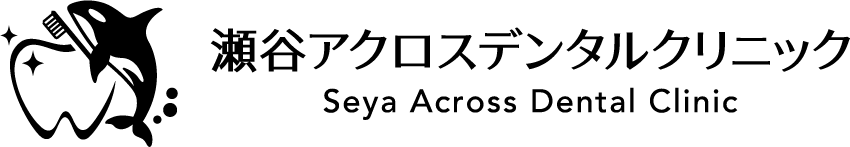2025年10月24日
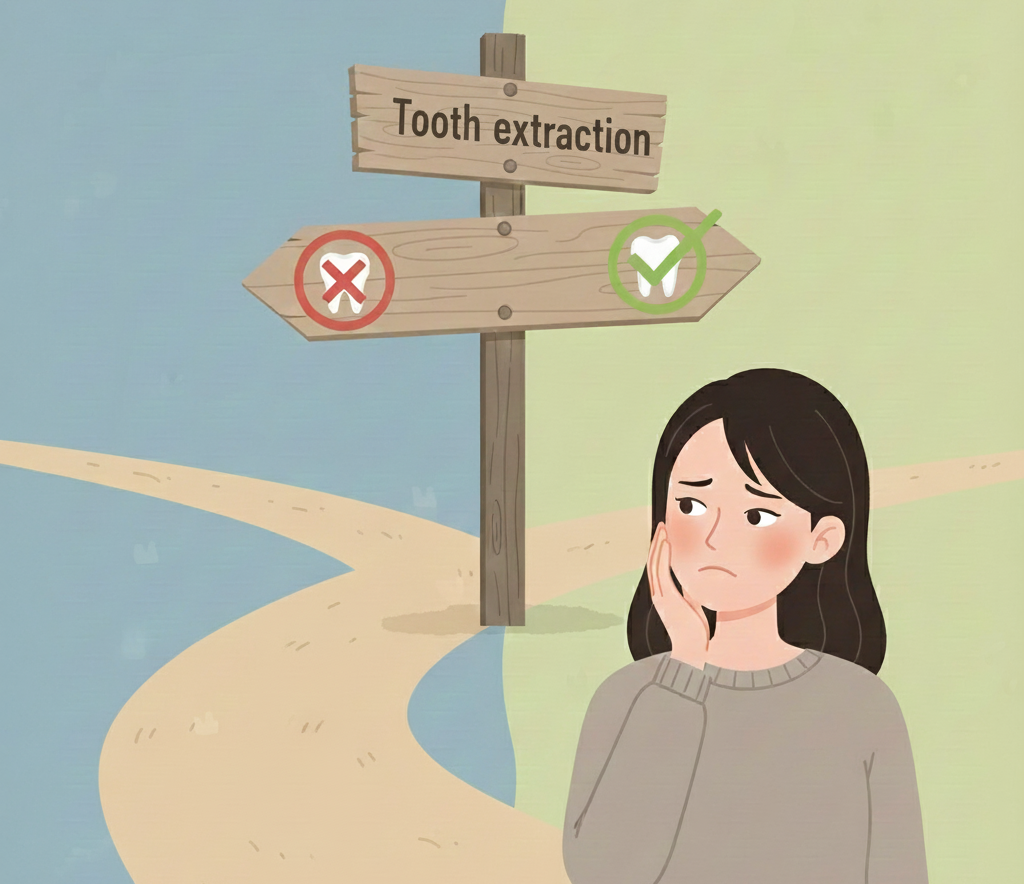
親知らずの「運命」は人それぞれ
「親知らず」と聞くと、「痛い」「腫れる」「抜歯」といったネガティブなイメージを持つ方が多いかもしれません。
上下左右に最大4本生えてくる可能性のある親知らずですが、果たして「自分は抜かなければいけないのだろうか?」と不安に思っている方もいるでしょう。
今回は、親知らずを抜歯することになる確率や、抜かずに済む人はどれくらいいるのか、そして抜歯が必要になる主な理由について、科学的なデータも交えて解説します。
「まっすぐきれいに生える」確率はわずか20%!?
親知らずの抜歯が必要になるかどうかは、「生え方」が大きく関わってきます。
通常、親知らずが他の歯と同じようにまっすぐ垂直に生え、かつ他の歯や噛み合わせに悪影響を及ぼさない状態になる確率は、残念ながら非常に低いことがわかっています。
複数の研究データによると、親知らずが問題なくまっすぐ生えてくる確率は、一般的に約10%〜30%の範囲です。
特に日本人を対象とした調査では、まっすぐに生える親知らずの割合は約20%であると報告されています。
つまり、約8割の親知らずは、斜めや横向きに生えたり、歯茎の中に埋もれたりする異常な生え方をしていることになります。
「抜かずに一生過ごせる人」は少数派
上下左右の4本の親知らずがすべて正常に機能し、一度も抜歯せずに一生を過ごせる人は、全体の2割以下であるという見解が多くの歯科医師の間で共有されています。
裏を返せば、約8割の人は、少なくとも1本は生涯のうちに抜歯の検討が必要になるということです。これは非常に高い割合だと言えるでしょう。
【知っておきたい豆知識】 ちなみに、日本人のおよそ3〜4人に1人(約20%前後)は、生まれつき親知らずの歯胚(たまご)がないとも言われています。この場合は当然、抜歯の心配もありません。
特に抜歯が必要になりやすい2つのケース
親知らずがトラブルを起こしやすい最大の原因は「スペース不足」ですが、その中でも特に、痛みや他の歯への影響で抜歯を推奨されやすい2つのケースをご紹介します。
ケース① 一部だけ生えている(半埋伏歯)
親知らずの頭の一部だけが歯茎から顔を出している状態です。これが、最も痛みと腫れの原因になりやすいタイプです。
なぜ問題か: 歯と歯茎の間に汚れ(プラーク)が溜まりやすく、ブラッシングによる清掃が非常に困難なため、親知らずや手前の歯が虫歯になりやすく、歯茎に炎症を起こす智歯周囲炎(ちししゅういえん)を頻繁に引き起こします。
ケース② まっすぐ生えているが噛み合わせが悪い
一見まっすぐ生えていても、上下の歯と噛み合っていない場合があります。
なぜ問題か: 噛み合う相手がない親知らずは、歯茎から過剰に伸びすぎてしまい、頬や舌の粘膜を慢性的に傷つけて口内炎や潰瘍の原因になることがあります。また、特定の歯だけが強く当たり、噛み合わせ全体を悪化させるリスクもあります。
その他のリスクが高い生え方
斜めや横向きに生えている(水平埋伏歯)
親知らずが手前の歯に向かって斜めや横向きに生えている状態です。
主なリスク: 手前の歯の奥側に常に食べかすが詰まりやすくなり、その部分が虫歯になるリスクが非常に高まります。また、手前の歯を圧迫し、歯並びのわずかな変化や歯根の損傷につながる可能性も無視できません。
完全に歯茎や骨の中に埋まっている
主なリスク: 稀に手前の歯の根を溶かしたり、周囲に嚢胞(のうほう)を形成したりするリスクがあり、定期的な経過観察が必要です。
まとめ:大切なのは「確率」ではなく「診断」です
親知らずを抜歯することになる確率は高いものの、すべての方が抜かなければならないわけではありません。
大切なのは、「自分の親知らずが今どのような状態にあるのか」を正確に把握することです。
瀬谷アクロスデンタルクリニックでは、親知らずの生え方や、将来的なリスクを詳細に診断し、「抜くべき親知らず」と「残して経過観察で済む親知らず」をしっかり見極めます。
親知らずの痛みや違和感がある方、まだ生えていないけど心配という方も、まずは一度、お気軽にレントゲン検査やCT検査、ご相談にお越しください。
参考文献(エビデンスとして)
親知らずの生え方に関する確率は、以下の研究やデータを参照しています。
・日本人におけるまっすぐな親知らずの割合に関する研究例
Kato, K., et al. (2004). Orthodontic considerations for the extraction of mandibular third molars. 日本矯正歯科学会誌, 63(3), 167-173.
・国際的な親知らずの生え方に関する研究例
Harris, E. F., et al. (2006). Maxillofacial anthropology: wisdom tooth impaction. Clinical Anatomy, 19(6), 524-531.
瀬谷アクロスデンタルクリニック
〒246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-23-35 アクロスキューブ瀬谷1-1
TEL:045-489-7400